こんにちは、みっくす!編集部のデイジーです。
今回は小学校入学にあたりどういう生活になったのかを綴っていこうと思います!
ちなみに下の子が幼稚園年中になるタイミングで流山市へ引っ越しをしているので、それまでは別の地域で暮らしていました。
うちの子の場合なので、参考程度に読んでいただけたらと思います。
まずすべきこと、特性アピール!
上の子を見ているので知ってはいましたが、全く心配なく、できることは自分のことは自分でスタイルで生活させていた感覚とはこうも違うのか!と思うほど心配だらけでスタート。
下の子は自閉症スペクトラム・発達協調性運動障害があったのものの穏やかで激しい特徴がなかったため、本人のお友達がたくさんいたほうがいい!という意見を尊重し普通級に進学。
トイレがいけない、読み書きがうまくない、人見知りで声がかけられない、着替えがうまくできない…等を担任の先生に本格的に授業が始まる前に、事前に特性を伝えておきました。
幼稚園は15人くらいの児童を1人または2人で見ますが、小学校は35人程度の児童を1人の先生が見ます。
声掛けも少なくなるだろうし、サポートといわれる先生がいたとしてもうちの子に付きっ切りというわけではない…。
その中でいかにうちの子に目をかけてもらえるか、大丈夫なように工夫してもらえるかがキーになります!
“できないこと”と“解決方法”~合理的配慮~
今、どの学校でも“合理的配慮”という「障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮」を 2016年4月に施行された「障害者差別解消法 (正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」で定められています。
要はできないことがあったら、求められたように、提案されたように最大限やってあげましょうね!というものです。
拒否したり、話も聞かぬまま放置したりしてはいけないってことですよね。
そこでそれをしてもらうべくアプローチしました。
- トイレがいけない問題(休み時間に行けない・さすがにオムツは無理)
- 読み書きができない問題(板書が写せない)
- 着替えができない問題(体育の時間に休み時間内に着替え終えられない)
- 人見知り問題(〇〇してくださいなどの意思表示が難しいので助けを求められない)
大きなところで最初に浮かんだのがこれらの問題です。
解決方法は担任の先生と話し合い、以下の通りにしました。
- トイレは事前に中の様子を母親と一緒に見させてもらう。休み時間ごとの声掛けをする。
- どこに何を書いていいのかわからないので、ノートに書く様子をタブレットを通して先生が大画面のテレビに映してくれて、書き方を分かりやすくしてくれる。子どもの席を1番前の席にして、都度様子を見てくれる。
- 着替えは一部手伝ってくれたり、前後が分からなかったり靴の左右も分からないので、間違っていたら声掛けをしてくれる。
- 様子を見つつ、声掛けしてくれる。
このように、なるべく大人数の中でも様子を見てくれて声掛けをしてくれることになりました。
面談の回数も多くしてくれることとなり、コーディネーターを交えての三者面談も設定してくれました。
大切なのはいかにアピールして、親の顔も知ってもらって担任の先生にも安心してもらうことかな?と。
クレーマーとかではなく、なるべく一緒に解決していきたいです!何かあったら先生も遠慮なく親に伝えてきてください!という関係性を築くことが何かあった時にも対処しやすくしてもらえるコツかな?と思います。
2年生以降の生活、合理的配慮
1年生はみんな学校に慣れるための期間。
つまりはそんなに個々に求められることは多くなく、何とかやっていけるものです。
先生のフォローのおかげもあり、トイレは克服できました!
着替え等については、クラスメイトのしっかりした子たちがうちの子を助けてくれたりしてよく「〇〇さんが手伝ってくれたよ!」と聞いていました。
2年生以降は板書スピードも書く量も増え、テストも難しくなります。
そこで合理的配慮のお願いをしました。
- 板書についていけない→タブレットで板書を都度撮ってもらい机に置いてもらう。
- 宿題の漢字が難しくすごく時間がかかる→読みに関しては音読形式ですませ、書きについてはノートに書く量を減らしてもらう。
- テストについて→合格点までの再テストは、3回までまたは、最後の一人にならないように配慮してもらい、終わらない量に関しては家で親と一緒にやるようにしてもらう。
担任の先生に相談をし、一緒に決めさせてもらいました。
担任の先生とよく話し合おう!
ここまで私は比較的スムーズに色々な対処をしてもらえたと思います。
他の学校の話を聞いていると、合理的配慮をしてくれなかったり、板書もタブレットを使って自分で写真を撮ってくださいと言われたり…
この記事を読んで、こういうことをしてもらえてる人もいるんだ!と知ってもらい“やってもらえること”を広げていってもらえたら…と思います!
子どもが『学校って楽しい!』と感じて、笑顔で登校してくれる日が増えること願っています。





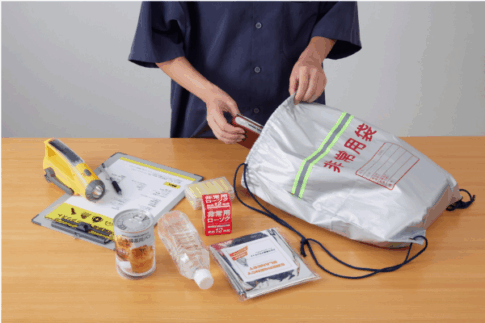







コメントを残す